1998.2.11 今年行った、音の授業の一部を紹介します
■ 音の波を調べる
「キューブセンサー(演示用一台)」の「音」の波形を調べました。 パソコンの画面は、ノートパソコンからテレビに出力しました。
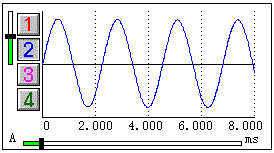
このセンサーは、Win版が出て、グラフのコピーなども簡単にできるようになりました。また、上のように1種類の波形だけでなく、何種類かのグラフを同時に重ねて表示することもできます。
音の実験
1998.2.11
今年行った、音の授業の一部を紹介します
■ 音の波を調べる
「キューブセンサー(演示用一台)」の「音」の波形を調べました。
パソコンの画面は、ノートパソコンからテレビに出力しました。
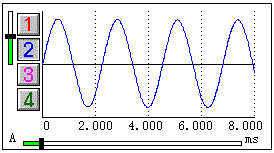
このセンサーは、Win版が出て、グラフのコピーなども簡単にできるようになりました。また、上のように1種類の波形だけでなく、何種類かのグラフを同時に重ねて表示することもできます。
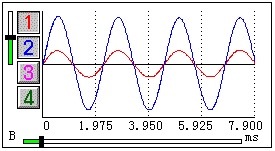 音の大きさの違い(音叉) |
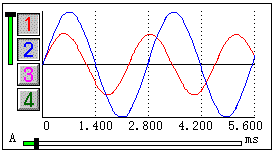 音の高さの違い(音叉) |
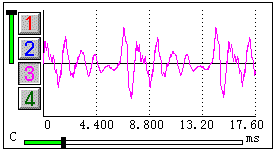 「あ」の音声 |
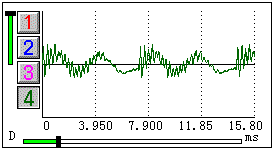 「い」の音声 |
■ 音速を調べる(生徒実験)
陸上のピストルを200m離れたところからビデオに撮影したものを用意し、これを使って音が伝わる時間をストップウォッチで測定させました。一人5回程度測定させ、中間の10回分の平均を求めましたが、200mを音が伝わる時間は0.5〜0.6秒ぐらいになり、音速は400m/秒〜330m/秒となりました。
■ 音速を調べる(演示実験)
正しい音速を求めるために、生徒実験の後に、専用の測定器で実験を行いました。
まず、1000分の1秒まで測れるタイマーを使ったもので、これを黒板に貼り付けます。これは、音でスタートし、光でストップするようになっています。
次に、6mぐらい離れたところに音が届くと光るストロボを置きます。これで準備OK。黒板の近くでオモチャのピストルを鳴らすと、ストロボを置いたところまで音が届く時間を測定してくれます。
結果は、360m/秒とやや大きめの値が出てきました。まあ、こんなもんなのかな?
| [斎藤の部屋(理科) Top Page] メニュー | mail: Saitou |